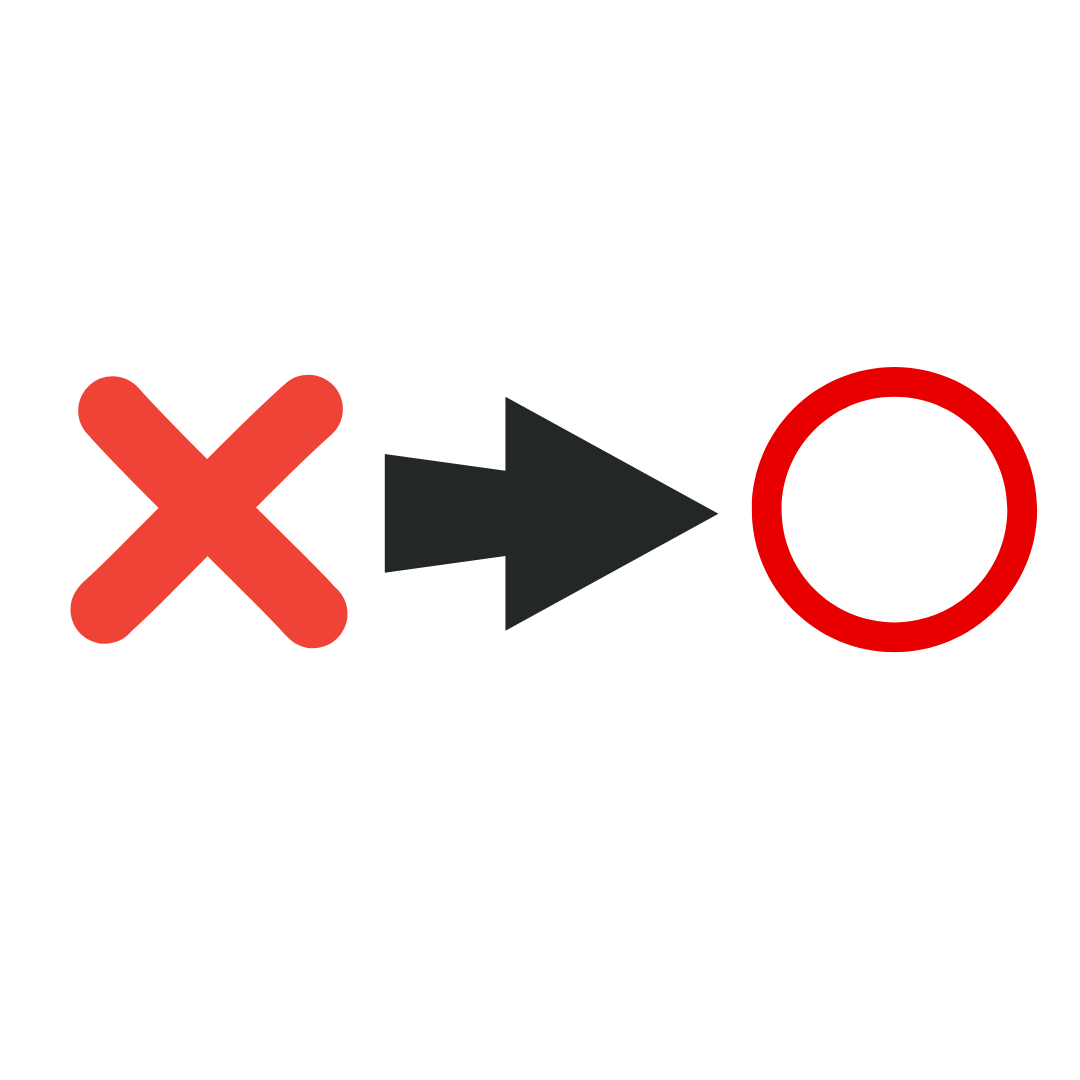「なあ、この問題、前にもやった気がするんだけど…。」
俺はこのセリフを、学生時代、1億回ぐらい言ったことがある。
ここに、数学という科目の大きな罠がある。
数学は「解く」教科じゃない。「再び出会う」教科だ。
数学の勉強って、たいていこうなる。
- 新しい問題を解く
- 解けない
- 解説を見る
- 「なるほど」って思う
- 次の日には忘れる(圧倒的あるある)
…ね?おかしいでしょ。
「わかった」ことと、「できる」ことは別人の仕業なのです。
脳のガソリンは限られている。◯△✖︎勉強法で“燃費”を上げよ!
そこで登場、「◯△✖︎勉強法」。
- ◯:初見で解けた問題(→この子はもう卒業。会いたくなったらまたでいい)
- △:解けなかったけど、解説を見たら「なるほど」って思えた&答えを閉じて解くことができた(→復習のゴールデンゾーン)
- ✖︎:解説を読んでも「???」が頭に並ぶやつor答えを何度も見返してやっと解くことができた(→今は歯が立たないけど、未来の自分が仲良くなれるやつ)
✖︎問題って、一見すると「できない」の象徴みたいに思える。
でも、実はここに自分の成長ポイントがギュッと詰まってる。
△で反復して“筋トレ”しながら、
✖︎は「いつか戦うラスボス」としてマークしておく。
そして数日後や数週間後、ふと解いてみたらスッと理解できる――
そんな“勝手にできるようになってる奇跡”が起きるのも、✖︎の魅力。
参考書、出しゃばりすぎ問題
でも実際、数学の参考書って異様に分厚すぎない?問題数が半端なく多いよな。
「このままだと俺の墓石に“因数分解”って彫られるんじゃ…」とすら思う。
だからこそ、やるべきは「全部を完璧に」じゃなくて、
「今の自分が向き合うべき問題を見極める」こと。
復習の効率化は、つまり“戦略”なのです。
✖︎と向き合える日は、成長した証拠
△は“今の自分”にちょうどいい負荷。
✖︎は“未来の自分”を待っている問題。
無理に今すぐ解けなくていい。でも、絶対に無視しないでほしい。
✖︎が少しずつ△になり、やがて◯になる。
この変化を感じたとき、「数学って…ちょっとおもしろいかも」ってなる。
数学は“脳の使い方”を学ぶ教科
数学が得意な人は、解くのが速い人じゃない。復習の設計がうまい人。
そして✖︎の問題すら、「今は取っておく宝箱」として丁寧に置いておく。
数学は、問題を解く教科じゃない。
「脳のリソースをどう振り分けるか」を学ぶ教科だ。
さあ今日も、◯に安心し、△で鍛え、✖︎に敬意を。
“できるようになる旅”は、いつも✖︎から始まる。